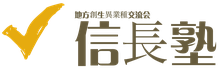この話は、私が一般社員からエリアマネージャーになるまで勤めた、日本一の体育会系営業会社、株式会社H通信で過ごした20歳〜25歳までの実録である。
THE SALES
〜元○戦士トップセールスが語る、実録・営業日誌〜
第4話
『最終日』
女性の名前はK原といった。
美人でも無く、決してスタイルが良い訳ではない。
が、どこかに妖艶な雰囲気を漂わせていた。
それは恣意的にそういった雰囲気を出そうとしているようにも捉えられた。
もちろん、タイプでも無い女性に雰囲気をもっていかれる程、異性に不慣れでは無かったので意にも介しなかった訳だが…。
その後、研修は事も無げに進んだ。
1日目、2日目とも私たちの営業部が取り扱う事になるSバンクの法人向け携帯電話について業界の動向や、知識研修がメインに行われた。

当時の携帯キャリアはたったの3社、
今の様なMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の技術は確立さえしていたものの、相対の特別プランとして一部のキャリアが用いていただけで一般化はされていなかった。
日本に流通している携帯電話の約半数がH通信が捌いた端末だと言われるほどなので、当然H通信内にも当時からMVNOを用いた相対の特別プランがあり、その研修も行われた。
業界については全くのシロウトで、今までは普通の携帯電話ショップで携帯電話を購入していた消費者側だった為、研修会場で耳にした特別プランにはその内容に心底度肝を抜かれたのを覚えている。
この業界にはいわゆる”ニギリ”というものが存在し、携帯キャリアと総代理店(H通信がこれに当たる)が販促数と販売奨励金を双方でコミットし合う文化があった。
H通信ほどの販売数ともなれば当然、その販売奨励金も他社とは比べ物にならない金額になるのも言うまでもない。
〈では、最後に皆さんが取り扱うSバンクの法人向け携帯電話(BM)について、この3日間で学んだ内容から販売ライセンステストを行います。〉
携帯電話を取り扱うのも無条件では無い、当然一定の知識レベルが求められる。
ただし、あくまで携帯キャリアが発行している民間の資格でしかないので、今回の様なある程度の研修さえ受ければ殆どの人が受かる内容である。(そうは言っても、研修担当の話では過去に落ちた人が何人かはいたみたいだが。)
〈では、今から合格者の名前を読み上げます。名前を呼ばれた方はライセンス証に載せる写真を撮影しますので別室に移動してください。〉
テストも終わり、合格者の名前が読み上げられていく。
その中には、初日に打ち解けたK石の名前もあった。
〈…K原さん、泉さん…〉
無事名前を呼ばれ安堵した。
その後、ライセンス証用の写真も撮影し、無事2日目の研修も修了。
残すところ、あと半日。
3日目はH通信の本社社内見学と携帯電話の倉庫など関連施設や関連会社の視察だという。
私は連日の疲れで寄り道もせず、研修生用に充てがわれていたウィークリーに戻りテレビを点け、コンビニで購入したビールを飲みながらベッドで横になっていた。
しばらくごろごろし、気がつくと夜の23時を回っていた。
『そろそろ明日に備えて寝ようか。』
そう思い、風呂に入る為服を脱ごうとしたその時。
〈ピンポーン〉
不意に玄関のインターフォンが鳴った。
『誰だ?ウィークリーにルームサービスなんてあったかな?』
〈ガチャ〉
玄関のドアを開けると、そこに立っていたのはあのK原だった…。

(文=泉了 写真はすべてイメージです)
営業処方箋 -実践家のための徹底使い切りBOOK
内容紹介
営業処方箋というタイトル通り、営業活動を成功させるために重要なエキスを、これほど簡潔にわかりやすくまとめた書籍は貴重な存在と言える。「実践書」というコンセプトにふさわしくサイズもB6版のポケットサイズに仕上げられており、毎日の営業活動にも携帯できる「使える実践書」である。能書きをだらだらと述べる本ではない。その意味では従来の営業ノウハウ本と一線を画しており、読破するのに時間はかからないが読み返すほどに手放せなくなる営業パートナー的存在となるだろう。営業の定義から始まり、マインドセット・目標設定・ラポール構築・営業アプローチ・クロージングの各段階について、考え方と具体的な営業技術が「即実践」できるように解説されている。営業経験の浅い読者にとっては基本の再認識と体得、長らく営業現場に身を置く読者にとっては自分自身の営業プロセスの再確認と問題点の発見及び具体的な改善・解決方法を見いだせる指南書=文字通り営業処方箋となるであろう。読めば読むほど、実践すればするほど本書に対するコストとPOI(投資回収率)が上がるようにという著者の誠実な執筆姿勢が伝わってくる。本文全右ページに「読書回数チェック欄」が設定されており、読者の皆さんにはぜひ「わかった」レベルから「できた」レベルまで、本がボロボロになるほど使い切ってもらいたいというのが著者の望みであろう。(S.O)