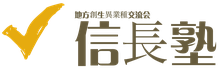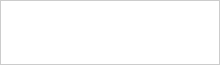これまでもこのブログで何度も取り上げてきたが、
飛騨の口碑では、日本で最初の高天原は奥飛騨の乗鞍だとされている。
(高天原は都の意であるため、神代でも何度か遷都されてきた)
つまり、飛騨高山は皇族、日本のルーツということだ。
乗鞍=祈り座が語源と言われており、古代飛騨の民はその磐座で祈りを捧げてきた。
それともうひとつ、奥飛騨には精神統一の行で日抱御霊鎮(ヒダキノミタマシズメ)という習慣があった。
それだ日抱=ヒダ、の語源だとされている。
飛騨の口碑文についての研究や視察報告詳細は、過去のアーカイブ記事を参照されたし。
アーカイブ記事:日本のルーツ飛騨高山
もっと詳しく知りたい方は飛騨の口碑研究の第一人者、
故・山本健造先生の著書「明らかにされた神武以前」をお買い求めください。
※信長塾も8年近くお世話になっている故・山本健造氏のお弟子である大場所長(福来研究所)と泉
さて、本日のタイトルについて、
我が国で天皇家が所有する三種の神器といえば、ご存じの通り下記の通りだ。
・八咫鏡
・天叢雲剣(草薙剣)
・八尺瓊勾
正史において、長くその存在や成り立ち、実際の姿形に至るまで神秘のベールに包まれているが、
飛騨に伝わる口伝では、特に八咫鏡と八尺瓊勾について下記の通り具体的な伝承が残っている。
まず、八咫鏡に関してだが、
飛騨=ヒダの語源でもあり、代々奥飛騨の地で精神統一の行としてつい百数十年前まで行われていた、
日抱御霊鎮の様子を写したものであるというものであり、
確かにそういわれたら、そう見えないこともないのだ。
※日抱御霊鎮をモチーフにした信長塾飛騨高山支部のロゴ
次に、八尺瓊勾についてだが、
以前このブログでも紹介した通り、初代神武天皇以前の皇(スメラ)は上方(ウワカタ)様と呼ばれていた。
その中で後の天孫降臨に繋がる統治の仕組みとして本家・分家制度を作られた15代淡上方(アワノウワカタ)様が、顔を知らない本家と分家の子孫たちが後々争うことのないように、親族の証として勾玉を持たせたことに由来しているとのことであるという。
※アワ=アワ山=乗鞍の古称
そして最後に、八岐大蛇伝説のある天叢雲剣(草薙剣)についても、一つ面白い情報がある。
ご存じの方もおられるかもしれないが、八岐大蛇は文字通り大蛇の化け物を指しているのではなく、大蛇=河川の氾濫、その治水の比喩や大陸からきたオロソ族など様々な説がある。
実は何を隠そう、岐阜が稲葉、井ノ口と呼ばれる以前は”無数の川があり、氾濫する”という意味を込めて八岐(ヤチマタ)と呼ばれていた史実がある。
つまり、八岐大蛇=河川の氾濫、退治=治水、という例えだとすれば、八岐大蛇伝説のある天叢雲剣(草薙剣)も岐阜県に関わりがあるということになる。
つまり、三種の神器はそれら全てが岐阜県にルーツがあるのでは?という仮説が立つのだ。
これらの仮説が立証されれば、日本のルーツが岐阜県、特に奥飛騨にあったという伝承の信ぴょう性を上げる根拠になるだろう。
更には、実録として、
終戦間際の1945年7月31日に昭和天皇が内大臣木戸幸一を呼び、草薙剣を疎開させる意向を伝えたのだが、なんと!その疎開先が飛騨の口碑で高天の原伝承も残る飛騨国一之宮・水無神社であったという記録が実際に残されている。
疎開が行われたのは終戦後、連合軍の進駐を控えた8月22日、宮内省の勅使が熱田神宮本殿で、新調した木箱に剣を収め、陸軍の協力で運び出し、9月19日まで水無神社に安置されたという。
ちなみに、その水無神社のご神体でもある霊峰・位山で生息するいちいの木からのみ、今上天皇の笏が代々作られているのもまた有名な話である。
奥飛騨に日本のルーツが存在していた、という点に関してはこれからも研究を重ねる必要があるとしても、
岐阜と皇族には密接な繋がりがある、ということはもはや疑いようのない事実なのではないだろうか。
信長塾飛騨高山支部では、
これら日本のルーツに迫る奥飛騨の伝承をコンテンツとしてイベントを定期開催している他、完全オーダーメイドでのツーリズム企画や研修プログラムのご要望も承っている。
興味がある方は下記支部ホームページより、詳細を確認の上お問合せいただければと思う。